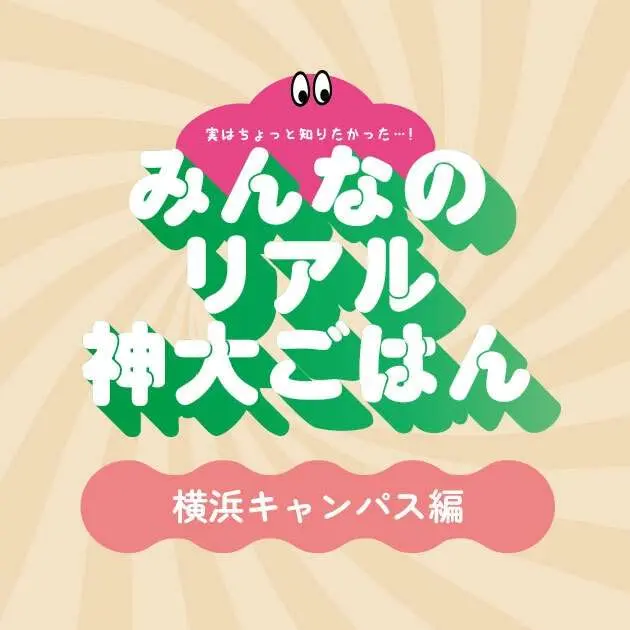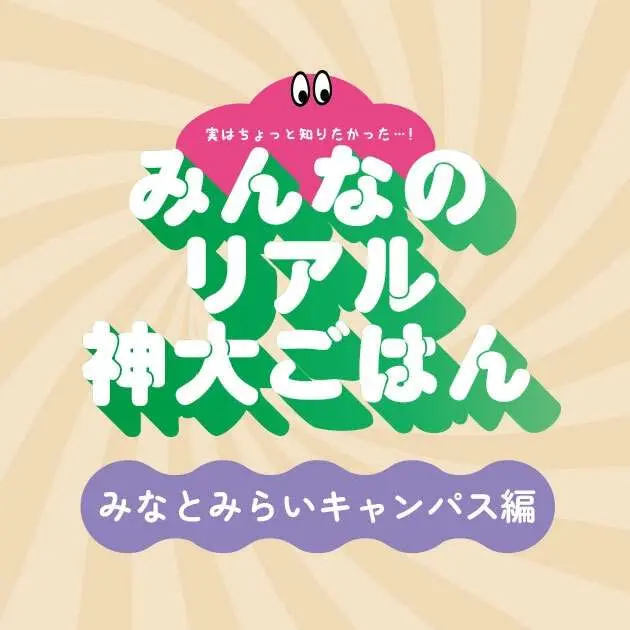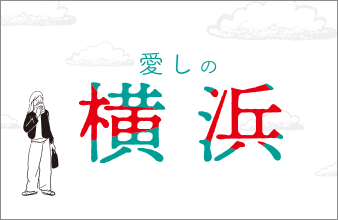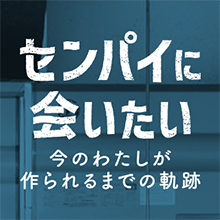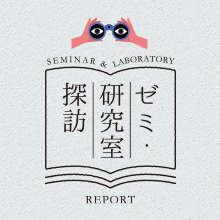横浜キャンパスで開催された
防災フェアを学生編集スタッフが
体験してきました

2024年11月14日(木)に横浜キャンパスで開催された、防災フェア。3年ぶりの開催となった今回は、大学・行政・企業が連携し、さまざまな体験・展示企画が出展されました。防災グッズの準備やハザードマップの確認、家族との連絡方法など、普段の生活の中でついつい後回しになってしまう災害への備え・・・実際にイベントを体験した学生編集スタッフが、その重要性をレポートします。
参加者プロフィール
-

法学部
法律学科2年 森紫織さん
-

経済学部
経済学科3年 苅谷和美さん※福島県出身、東日本大震災で被災した経験有り。
-

経営学部
国際経営学部3年 三浦知樹さん
起震車による地震体験

- 三浦さん:
- 地震の恐ろしさをリアルに実感できる貴重な体験。立っていることが難しく、家具や物が転倒する感覚が伝わり、家の中で地震が起きた時の恐怖が想像できました。地震の時にパニックにならず、どう行動するかを日頃からしっかり準備しておくことの大切さを痛感しました。
- 苅谷さん:
- 地元では地震車の体験がほとんどなかったので、今回が初めての体験です。思ったよりも大きな揺れが再現されていて、車から落ちそうになる恐怖感がありました。
ただ、実際の地震に似ているかと言われるとそうではなく、あくまでも「揺れ」の再現に留まってしまうなと感じます。
揺れによって立てなくなるのは同じでしたが、初期微動の音、周りの物が崩れる音、緊急地震速報の音、自分の拍動や呼吸が乱れる感覚……。その後の安否確認の連絡やニュースに張り付いて情報を集める作業など、異なる点を挙げるときりがないです。
煙避難体験

- 森さん:
- 煙の中を這うという経験を初めてしました。人工的に作った煙でさえほんの少し先が見えず、試しに少し嗅いだだけでむせそうになるほどだったので、実際の黒煙などだと致死性が高まるのも必然かつ、口鼻をしっかりおさえる大切さを実感しました。
- 三浦さん:
- 予想以上に怖く、難しいものでした。煙が充満した環境では、まず視界がほとんど遮られてしまい、方向感覚を失いやすく、自分がどこにいるのかわからなくなってしまいます。
日頃から火災時の対処法や心構えを確認し、「落ち着いて行動すること」の大切さを胸に刻んでおこうと思いました。
担架救助体験

- 苅谷さん:
- 即席の担架は、思ったよりも安定していました。毛布を棒に巻いただけという簡単な仕組みだったので不安でしたが、毛布が動くようなこともなく、簡単に持ち上げられてしまいました。
棒と毛布を集める余裕ができるのは、災害がひと段落したらだとは思いますが、家にあるもので作れるので、緊急時にもってこいだと思いました。 - 三浦さん:
- 布団と洗濯竿を使った担架作りの体験を通して、単に材料があればよいわけではなく、災害時や緊急時に安全に活用するためには、正しい折り方や手順といった確かな知識が不可欠であることを実感。
消防署の方が丁寧に注意点等を教えてくれました。
非常トイレ体験

- 苅谷さん:
- 凝固剤で固まる簡易トイレですね。もし、ごみ収集ができなかったら、どこに保存しておくかも考えておく必要がありそうです。
3.11の時は、断水はあったものの下水管が生きていたので水を汲んできて注げば流れてくれましたが、下水管破裂の可能性も考えて備えておくべきですね。 - 森さん:
- 食事や水のことに気を取られており、災害時のトイレについて失念していたため、展示されている非常トイレを見てハッとしました。
排泄物を放置することでただでさえ悪い衛生環境がさらに悪くなり、感染症などを引き起こす。でも人間は排泄をしなければ生きていけない。そう思うと非常トイレもしっかり備える必要がありますね。
非常食

- 森さん:
- 非常食=保存を優先としているため味がほぼないパサパサしたもの、というイメージを持っていたので、色々な味があるに加えてアレルギーフリーといった対応がされていることを知り、現代の災害支援物資の進化を目の当たりにしました。
- 三浦さん:
- プレーン味を試食させてもらいました。
通常のクッキーに比べてカロリーが高く、少量でもしっかりとエネルギーを補給できる点が印象的でした。また、味も食べやすいため、非常時だけでなく普段の携帯食や軽食としても役立つと思います。
イベント全体を通して

- 森さん:
- 体験の他に、水の貯蓄や非常時に使う栓などが使えるようになる期間などの知識を教えていただきました。私たちの世代は3.11を自ら体験しているため災害教育は比較的受けていますが、それでも初めて聞くことが多かったです。今年8月、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が初めて発表され、いつ大災害が起きるか分からない日本。こういった災害関係の活動は任意ではなく、必須講義や自治体などでも頻繁に行う必要があると考えました。
- 苅谷さん:
- 今回は、基本となる知識を身に付けられるような体験が多かったと感じました。これまで話してきたもの以外にも、アルミの防寒シートや防災マップなどのブースがあり、これらも家に設置しておくべきだと思いました。他には、電池式の簡易ライト、災害用のポータブル電源やラジオも準備しておくと便利です。
災害はいつ起こるかわかりません。そのため、食糧と寒さ・暑さ対策用品は生き残るためにかなり重要です。津波によって溺死には至らなくても、身体が濡れてしまい低体温症で亡くなった方もいます。まれにですが、災害による異常気象も発生するため、衣替えをしても何着かはすぐに出せるように手元に残すようにするなど、何かしらの対策をすることをおすすめします。
3月11日は、大きな揺れがある程度落ち着いた後、雪が降りました。電気もガスも食糧もない中で寒さを凌ぐのは本当に大変でしたよ。 - 三浦さん:
- 今回の防災フェアを通じて、実際に体験することの大切さを強く感じました。防災についての知識を理解しているつもりでも、実際に起震車での地震の揺れや、煙避難体験、非常トイレの使用や担架搬送等を体験すると、想像以上の難しさを感じ、知識が必要であるということを実感できます。
今後も日常生活の中で災害への備えを心がけていきたいです。